活動報告
横浜市立大学附属病院医師働き方改革WG長就任
医師の働き方改革について
2024年4月より日本全国で医師の働き方改革が展開され、タスクシェア・タスクシフトをはじめ様々な取り組みが各施設で行われております。
横浜市立大学附属病院でも他施設同様、医師の働き方改革を推進しています。
この取り組みは、医師が質の高い医療を提供し続けながら、教育・研究活動にも従事できるよう、労働環境を改善することを目的としています 。
働き方改革推進プロジェクトの目的と背景
附属病院では、医師の働き方改善のため、「医師負担軽減実行ワーキンググループ」を組織し、各方面からの意見を統合し、負担軽減の実現に寄与するように定期的に話し合いを行っております。
また、定期的に「医師の働き方改革瓦版」にて現状につき職員に共有しています。
これは、附属病院でのルールや制度改正、よくある質問などを通して、医師の働き方改革について理解を深めていただくことを目的としています 。
令和7年度大井准教授が「医師負担軽減実行ワーキング」のワーキング長として就任し、働き方改革の推進を行っています。
今回6月30日付瓦版で大井准教授が挨拶をしています。
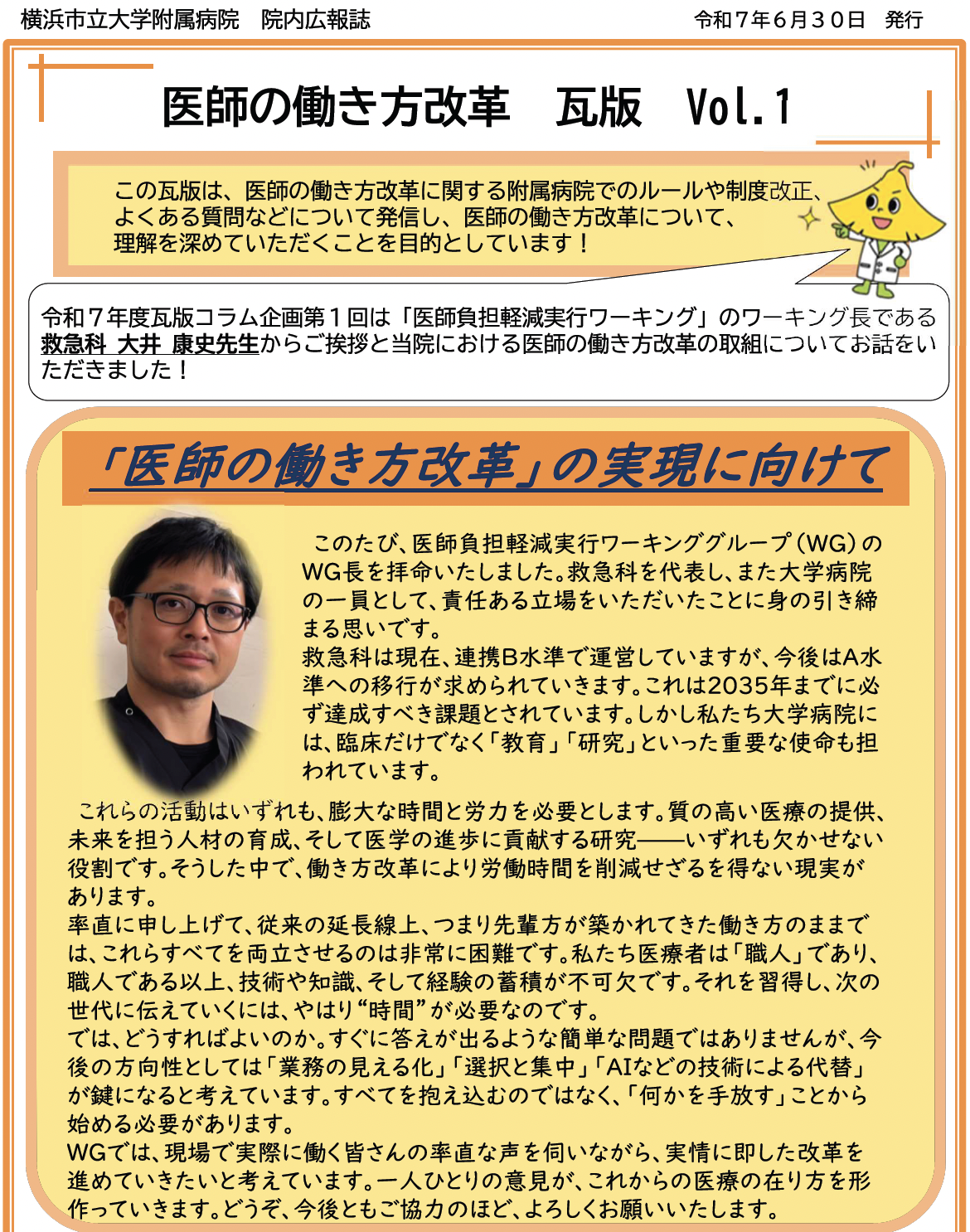
内容として:医師の働き方改革における課題
医師の働き方改革を進める上で、いくつかの重要な課題があります。
まず、救急科は現在、連携B水準で運営されていますが、2035年までにA水準への移行が求められています 。しかし、大学病院には臨床だけでなく、「教育」や「研究」といった重要な使命も担われており、これらの活動は膨大な時間と労力を必要とします 。質の高い医療提供、未来を担う人材の育成、医学の進歩への貢献はすべて欠かせない役割でありながら、働き方改革による労働時間削減が避けられない現実があります 。
従来の働き方の延長線上では、これらすべてを両立させることは非常に困難であると率直に述べており、医療者は「職人」であり、技術や知識、経験の蓄積が不可欠であり、それを習得し次世代に伝えていくためには「時間」が必要であると指摘しています。
この課題に対し、今後の方向性としては「業務の見える化」「選択と集中」「AIなどの技術による代替」が鍵となると考えられています 。すべてを抱え込むのではなく、「何かを手放す」ことから始める必要がある考えています。
医師負担軽減実行ワーキンググループでは、現場で働く皆さんの率直な声を伺いながら、実情に即した改革を進めていく方針です 。
一人ひとりの意見が今後の医療のあり方を形作っていくため、継続的な協力が求められています 。
今後も附属病院において、医師の働き方改革への改善を含め、大井准教授が中心となり、より良い方向性を考えながら、進めていく所存です。









